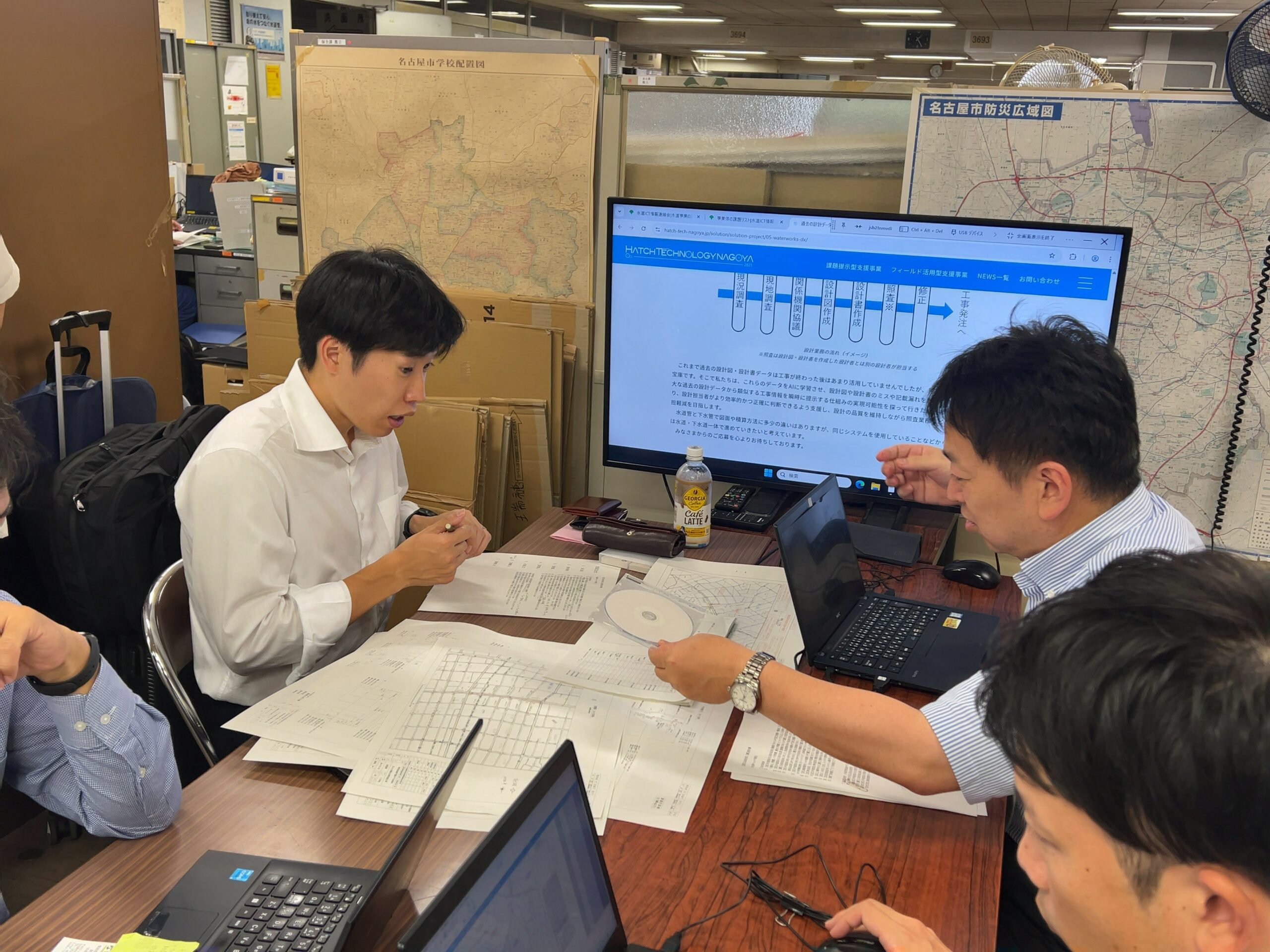Hatch Technology NAGOYA課題提示型支援事業では、現在8つの実証プロジェクトが進行中です。今回はその中から、上下水道局 配水設計課・下水設計課と株式会社KK Generationが連携して取り組むプロジェクト、「過去の設計データをAIで資産化!上下水道管の設計業務の効率化プロジェクト」の進捗をお伝えします。
実証背景
名古屋市の水道管の総延長は約8,400km、下水管は約7,900kmに達しています。これらの多くは高度経済成長期に整備されたものであり、今後、更新(布設替え・改築)のピークを迎える見込みです。上下水道局では、財政負担を平準化しながら計画的に更新を進めており、改築更新のための設計は、上下水合わせて年間300件以上にのぼります。近年は、従来以上に老朽化対策や地震対策の推進のほか、名古屋駅周辺では大規模なプロジェクトが複数同時に進行中です。このため、設計部門では調整業務や設計業務が増加しており、従来にも増して負担がかかっています。
一方で、全国的に公営企業の職員数は減少しており、名古屋市上下水道局でも同様の傾向が見られます。限られた人数で増加する設計業務に対応するためには、抜本的な効率化が不可欠です。今回は設計業務の中の照査業務に焦点あて、これについてAIで効率化が図れないかと考えたものです。
この課題に対し、株式会社KK Generation(以下、KKG社)から、建設図面に特化した独自の「検図・照査AI」技術を上下水道の分野に応用する提案がありました。過去の設計データをAIに学習させることで、図面と積算書など複数の書類間の数値の不整合や記載漏れの疑いがある箇所をAIが自動で検出するシステムの開発・検証に取り組みます。
現場のリアルを理解するために、市役所で現地打合せを実施

実証プロジェクトのキックオフ会議に続いて、9月22日に名古屋市役所西庁舎に配水設計課・下水設計課とKKG社のメンバーが集まりました。まず、上下水道局からKKG社に対して、実際の設計図や設計書の内容について説明し、その後、今後プロジェクトを進める上での技術的課題の共有や実証の進め方について話し合いました。
この対面での打合せは、プロジェクトを進める上で非常に有意義なものとなりました。水道・下水道の設計図や設計書には、一般的な建設図面とは異なる独自の決まりがあり、図面を見せながら独自の記載法や、一見すると定義が曖昧な取り決め、照査業務において設計者が苦労している点などをKKG社に直接伝えました。こうした設計者の生の声を反映させることが、AIの精度を高め、より実用的なツールへとつながると考えています。
その後、令和4年度から令和6年度の過去の設計データをKKG社に提供し、開発が本格的に始まりました。10月からは毎週Webにて打合せを行い、進捗状況の確認や疑問点の解消を逐次実施しています。11月中旬には最初のプロトタイプがKKG社から提供される予定であり、今後はそれを利用して検証を進める計画です。できる限り多くの設計図で照査の精度、速度及び有用性を確認する予定です。
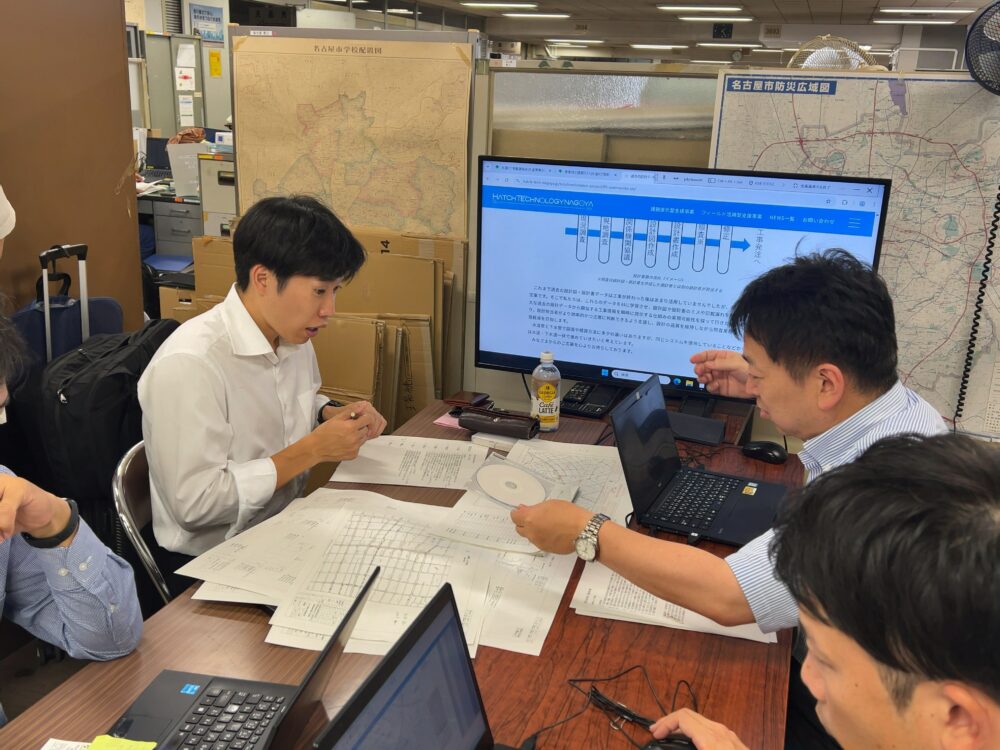
目指すはAIとの協働 ― 未来の働き方を検証する
今回のプロジェクトで設計図や設計書の照査業務すべてをAIに代替することは、費用や期間、取り組みの内容から非常に難しいと考えています。まずは、照査項目リストから水道10項目、下水道10項目を選定し、これらに関してAIが人間と同等以上の精度で、かつ迅速にチェックできる「可能性」を探っています。
過去の膨大な設計データには、これまで明文化されてこなかったベテラン職員の知見や判断基準が埋もれています。将来的には、AIにこれらを学習させることで、照査業務の精度を維持しつつ時間短縮を図り、職員が調整業務やより高度な技術力が求められる業務に注力できる環境を整えることが目的です。
KKG社は、人間の経験に基づく「暗黙知」を過去の設計データから学習する「図面×AI」の技術を有し、独自のプロダクトをリリースしています。同社は既に建設分野で多数の実績がありますが、今回の上下水道分野における取り組みは新たな挑戦です。
本プロジェクトに向けた意気込みについて、KKG社の市川さんは次のように語ってくださいました。「今回の名古屋市上下水道局様との実証実験を通じて、現場のリアルな業務環境でAI技術の実用性を検証し、照査業務の効率化と技術継承の両立を実現してまいります。図面認識に特化したAI企業として、全国の自治体インフラの持続可能な維持管理に貢献できるよう、今後も技術開発に邁進してまいります。」
今後もHatch Technology NAGOYAのページで実証プロジェクトの取り組みを発信していきます。FacebookやXでお知らせしていきますので、フォローよろしくお願いします。